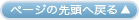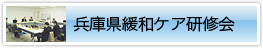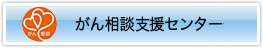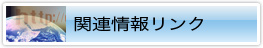第2回幹事会が令和7年2月13日(木)にWebにより開催され、兵庫県内の地域がん診療連携拠点病院等45病院及び関係病院等2施設・2団体の代表者が参加した。
※ 幹事、事務担当者等、代理を含め98名が出席 (欠席施設等:2施設、1団体)
(1)前回幹事会及び協議会議事録の確認
昨年6月6日開催の第1回幹事会議事録は、本協議会のホームページに掲載されているので、内容の確認をしていただきたい。
(2)がん対策について (資料2/PDF: 1.3MB)
①兵庫県内のがん診療連携拠点病院等の指定状況等
国指定拠点病院、県指定拠点病院、準じる病院等、特に変更とはありません。がんゲノム医療連携病院では、加古川中央市民病院が新たにがんゲノム医療連携病院に指定された。連携医療機関としては、県立がんセンターです。今回の変更点は以上のとおりです。
②がん医療体制等について
がん診療連携拠点病院の指定要件に関するアンケートは、がん対策基本計画において、国及び都道府県はがん医療が高度化する中で引き続き質の高い医療を提供するため、地域の実情に応じ均てん化を推進し、持続可能な医療の提供に向けて拠点病院等の役割分担を踏まえた集約を推進するとされている。これによって、がん診療拠点病院の現状課題を把握するためにアンケートを実施し、国指定18病院、県指定8病院のほとんどの病院から回答をいただいた。
調査内容は、指定要件のうち特に診療実績、診療従事者等の確保の困難さの有無について調査を実施した。要件を満たしていても将来、特に指定更新の時期まで確保は困難と予想される項目などについて回答をいただいた。アンケートは現在取りまとめ中だが、調査結果については、3月4日開催予定の「健康づくり審査会対がん戦略部会」で報告し、次の協議会(令和7年4月)で報告する予定である。この結果を踏まえて、県としてどんな対応がとれるか来年度検討したい。
兵庫県でがん患者の療養生活の質の向上に向けて実施している事業の中で、「三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業」は、三大疾病(がん、脳卒中、心血管疾患)の治療のために一時休業で従業員の代替職員の賃金に対する補助制度である。働きながらがん治療を受ける方を支援するためで、対象者は健康づくりチャレンジ事業(常用労働者300人以下)、その他中小企業(従業員数100人以下)となっており、対象費用は治療のために休職する従業員の代替職員の賃金で、補助率は2分の1、上限額が1期10万円、通算で7か月です。その他の疾病でも最大で休暇の取れる間で算定した額を設定している。この制度を創設してから周知はしているが、活用が十分でないとの指摘もあるため、是非このような事業があることをがん相談支援センター等で周知をお願いしたい。
若年者の在宅ターミナルケア支援事業は、終末を向かえた若年で18歳から40歳のがん患者が住み慣れた自宅で最後まで安心した生活を送れるように、自己負担1割で利用できる訪問介護サービスを提供する事業です。特に40歳以上については介護保険制度等で支援が行われ、18歳以下については小児慢性特定疾患制度で支援が受けられるのに対して、18歳から39歳の方については公的支援が非常に少ないことで、県独自で県と市町の協調事業として実施している。支援内容は訪問介護で、身体介護は生活援助の利用料(利用は週3回まで)となっている。特に在宅ターミナルでは支援が十分得られていない方もおられるので、この制度の周知をお願いしたい。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は、B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん重度肝硬変患者の特定を踏まえて、患者の医療費の軽減を図ることで国の調査研究事業として実施している。B型・C型肝炎ウイルスは、新薬で治療成績が向上しているが肝がん重度肝硬変で苦しんでおられる方も多いことから、入院・外来医療費を軽減するための補助制度が平成30年につくられた。対象者は年収370万円未満、対象経費は24か月、高額療養費の限度額を超えた月が既に1か月以上ある場合は2か月目から自己負担金は1万円に減額する制度です。実績は兵庫県内でも延べ数で年間200件位と少ないことから、国からも周知依頼がきている。がん相談支援センターで、この制度の周知をお願いしたい。
令和7年度厚生労働省のがん対策予算案は昨年12月末に発表されている。がん対策としては、351億円と昨年度並みということです。予算の枠組みは、がん予防、がん医療、がんとの共生と昨年度とあまり変更がない状況です。また、来年度の県の助成事業については、4月の協議会で説明させていただきます。
〇若年者の在宅ターミナルケア事業に対する要望(情報・連携部会長)
この事業は本当に助かっているが、名称が「ターミナルケア」とか「終末期」とか、かなり刺激的な言葉がある。終末期という言葉は、厚生労働省でも使わなくなってきている。ターミナル事業はもう命がないから使うといった感じになると、まだ頑張りたいとか、若い人は対象でない、心の準備ができていない方には紹介ができない。ターミナルケアと書かれているから、制度があっても使わずにギリギリまで治療を頑張る方もある。市によっては既に対策済みのところもある。県においても事業名称を広報しやすいように修正を検討いただきたい。制度の周知や紹介がしやすくなると思う。
〇二次医療圏についての質問(ひょうごがん患者連絡会)
阪神南医療圏と阪神北医療圏、中播磨医療圏と西播磨医療圏は、それぞれ統合して阪神医療圏と播磨姫路医療圏になっている。兵庫県のホームページは更新日が2020年3月の古いまま掲載されている。がん診療連携協議会のホームページは新しい情報で掲載されている。これについて、どう考えているか。
⇒ 二次医療圏については医務課の所管ですが、従来10圏域だったが医療計画の見直しにより中播磨と西播磨、阪神北と阪神南を統合して8圏域となっている。一方、がんの医療圏は従来の二次医療圏にとらわれず柔軟な対応ができるとなっているので、従来どおり10圏域という取扱いをしている。(疾病対策課)
⇒ ひょうごがん患者連絡会の理解としては、がんの医療圏毎に国指定のがん診療連携拠点病院が、今後整備されていくと考えているがそれで良いか。(ひょうごがん患者連絡会)
⇒ 国の整備指針では、がんの医療圏毎にがん診療連携拠点病院を整備することになっている。病床数配分の基準となる二次医療圏と一致させる場合があるが、兵庫県の場合は、少し異なる扱いをしている。1つのがんの医療圏に1つのがん診療連携拠点病院を整備する方針に変わりはない。(疾病対策課)
⇒ わかりました。今後とも整備、宜しくお願いします。特に西播磨と丹波は、地域がん診療病院になっているので、国指定の地域がん診療連携拠点病院を目指して頂きたい。(ひょうごがん患者連絡会)
〇肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業についての質問(ひょうごがん患者連絡会)
平成30年、この制度の利用実績が厚労省の見込数の1%だった。令和3年に制度が改正されたが、実績は厚労省見込数の3~4%だった。当時の厚労省大臣が見込数の7割位いかなかったら予算を減額するという話だったので、各病院でこの制度の周知をお願いしたい。
(3)協議会・幹事会並びに各部会の令和6年度活動報告並びに令和7年度活動計画について
(資料3/PDF: 6MB)
①「協議会・幹事会」関連
令和6年度は、4月11日に協議会、6月6日に第1回幹事会、第2回幹事会が本日2月13日です。第14回ひょうご県民がんフォーラムは、10月19日に兵庫県看護協会会館で開催した。
令和7年度の活動計画は、第20回協議会は4月17日に、第1回幹事会は6月19日に予定している。第2回幹事会の開催日は今のところ未定です。第15回ひょうご県民フォーラムは、ACPに関する内容で、神戸市立医療センター中央市民病院の担当で開催を予定している。
②「研修・教育」部会関連
令和6年度の活動報告は、11月22日、29日、12月6日にがん看護コアナース育成セミナーを開催。テーマは「不眠は夜の問題ではない」で12名の参加があった。研修・部会セミナーは10月5日、テーマは「消化器がんに対するロボット手術の現状と未来」、企画は川崎病院、現地会場とWebのハイブリット開催。会場23名、Web37名、計60名の参加があった。放射線セミナーは10月12日、「直腸がんの診断と治療」をテーマにハイブリッド方式で開催。会場32名、Web125名、合計157名の参加があった。検査セミナーは12月14日、「見えない敵とどう戦うかーがんと微生物に対する両面作戦―」をテーマに、ハイブリットで開催。会場41名、Web53名の計94名参加頂いた。薬剤師セミナーは2月8日、ICIによるirAB・薬剤師外来」をテーマにハイブリッド方式で開催。会場22名、Web237名と沢山参加頂いた。がん診療連携拠点病院を対象とする兵庫県がん化学療法チーム研修会は、11月30日に開催、テーマは「がん治療における妊孕性温存」、3チーム13名参加があった。ひょうご県民がんフォーラムは、先程、説明があったとおりです。
令和7年度の活動計画は、がん看護コアナース育成セミナーの開催は詳細未定ですが、3日程度に分けて実施します。兵庫県がん化学療法チーム医療研修会も詳細は未定ですが開催します。セミナーに関しては、研修教育部会セミナーは10月11日、神戸市教育会館大ホールで開催します。テーマは膵がんの診断と治療の最前線です。関西労災病院の企画で、ハイブリット方式で実施します。放射線セミナーは10月25日、テーマは乳がんの診断と治療-update-で、こちらもハイブリット方式で開催します。検査セミナーは12月6日又は12月13日でテーマ、会場も決まっていません。薬剤セミナーも詳細は未定です。ひょうご県民がんフォーラムは、先程案内があったとおり、ACPに関する内容で、10月15日の予定です。
先ほどの研修教育部会セミナーのアンケートは26名と少なく、あくまで参考ということですが、職種は医師職10名、看護師8名、他のメディカルスタッフの方も参加いただいておりました。開催時期はいつでもが77%、開催時間帯ですが、以前、私が平日開催はいかがでしょうかということでアンケートを取った。土日は都合が悪い方はここに入っていないのですが、それでも平日夕方、午後を希望される方が31%、8名ですがおられたということです。今後、これは引き続き考えていただけたらと思います。土日は出来るだけリフレッシュして頂いて平日の診療に充実して従事して頂きたいというのが私の希望です。基調講演1・2、特別講演3の内容は、概ねよくわかったということで満足いただけたのではと思います。セミナーのテーマの希望として、肺がん、膀胱がん、婦人科・泌尿器科手術、がん治療におけるチーム医療ということで、今後の参考にさせていただきます。その他意見として、最新治療について学べた。消化器がんの治療について学べたなど。Web配信のためのカメラが視界の邪魔になった。は今後の反省材料にしたい。
③「情報・連携」部会関連
令和6年度活動報告は、今年から業務改善の1年目ということで、部会を年4回から2回に減らして実施した。まず9月28日は対面開催で就労支援を3か年計画で行った。就労支援は概ね軌道に乗ったので、集大成ということで実施している。3月8日はPDCAとピアサポートのフォローアップ研修を合わせて1日で行う形にしている。事務局会議は、昨年度の毎月開催から隔月開催に減らして実施してきた。
令和7年度の活動計画は、部会を年2回にまとめ、事務局会議も隔月に行うようにしている。相談員研修に関しては企画、指導者の育成、ピアサポーター関連の事業ということで、それぞれの小グループでタスクを進める。今年度から業務改善を推進しており、特に管理的立場の方の会議出席数も増えている。来年度の計画にあるように小グループ分けの変更を進めているが、まだ目標の形になっていない。グループ毎の業務量の調整は、各病院のマネジメントの立場の方々の意見交換が必要と思うが、部会の出席者は実務者が中心となっているのが実情である。
例えば一部グループから業務について調整依頼があった場合、全体の調整になるので、事務局会議に組織マネジメントの経験がある方に病院代表として意見を頂きたい。数年以内に実務者中心の会議ではなく、ある程度マネジメントに携わる方が基本的に出席いただいて、実務者の方はオブザーバーとして現場の意見を頂く形を想定している。これができなければ働き方改革を踏まえての業務量調整は困難であることは、昨年ご相談したとおりです。実際に小グループ活動などで、実務者が馴れていないような公的なタスクとか企画立案などについて、本来必要のないジョブトレーニングが発生して、双方に大きなストレスとなっていると複数のご意見を頂いている。
ピアサポート関連では、ピアサポートのグランドデザインについて病院としての話とか県や患者会に病院としてどんな依頼をするといった事項を話し合う段階に来ているので、小グループではなく事務局会議に格上げしたいと考え、格上げするとなると事務局会議にマネジメント力のある方の参加がなければ進まない。各小グループの助けについては、外部公式予算の動くところについて様々な手続きが必要になるので、このあたりを簡素化したいと考えている。
なお、ピアサポート養成事業は、本来は兵庫県の事業で、これまで情報・連携部会がかなり主体になって運営に携わっていたので、県に移管をお願いして小グループ活動の業務負担をお願いしたい。これは県の方と調整したいと思っているが、協議会の後押しもお願いできればと思います。この数年の情報連携部会の参加については、今までの実務者中心からマネジメント経験のある方へ移行していただけるよう、各病院の方々も将来計画の中に織り込んでいただきたい。
〇がん相談支援センターについての質問(ひょうごがん患者連絡会)
国指定のがん診療連携拠点病院で、他病院の患者さんが別の病院のがん相談支援センターに行って相談することは可能ですか。
⇒ 制度的には可能です。拒否しているがん相談支援センターはないと思われます。(情報・連携部会長)
⇒ 去年、肺ゆう会でそのような事例があった。ある病院で相談したが不安で、がん患者会で対応不可能だったので他病院を勧めたら、電話で予約を取る段階で「しっかりした病院で相談を受けているので、ここでは受けられない」「他病院の患者さんの公的な支援、或いは就労支援、心理的な支援はできない。自分の病院で相談するように」と断られたとがん患者連絡会に相談があった。(ひょうごがん患者連絡会)
⇒ 個別な案件になるので、何か特殊な状況があると思いますが、一般論では他病院でも相談 は受けられます。その病院にはがん相談支援センターがない病院だと思われる。自分の病院 で相談しにくいから他病院へ相談した場合は、病状から一般的な相談になる。できればご自身の病院のがん相談支援センターで相談された方が良いのではという答えは十分想定できる。(情報・連携部会長)
⇒ 予約を取らないと、がん相談支援センターにアクセスできないので、受け付ける方が先生のような認識をもって対応いただくとありがたい。(ひょうごがん患者連絡会)
④「がん登録」部会関連
令和6年度の活動報告は、6月26日にがん登録部会をWebで開催した。参加者41施設50名。議事については、今年度の院内がん登録スケジュールとQI研究に関わるデータ提出スケジュールについてです。院内がん登録実務者ミーティングについては、第1回が11月14日Web開催。担当病院は県立尼崎総合医療センターで参加者は94施設217名です。講師は国立がん研究センターから講師を迎えて実施した。第2回目は1月31日にハイブリットで開催。担当病院は加古川中央市民病院で参加者は35施設から参加頂いた。テーマは、兵庫県がん診療連携協議会のホームページ公表案でした。がん登録実務者研修会の開催は、9月20日から10月31日に動画配信した。テーマは全国がん登録の届出実務とデータ分析ということで、国立がん研究センターに講師を依頼し、視聴回数は240回だった。
令和7年度の活動計画及び今後の課題は、がん登録部会は6月に開催予定。院内がん登録実務者ミーテティングについては、年2回ということで、講義形式で11月、院内がん登録集計結果報告を2月に予定している。全国がん登録に関する研修会は、開催時期、内容については未定です。
手元資料は、協議会のホームページに掲載する院内がん登録情報です。2022年の症例を施設別部位別、がん登録件数を掲載している。大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、そして前立腺がんを加えた5つのがんについて公表します。参考にしてください。
⑤「緩和ケア」部会関連
令和6年度の活動報告は、緩和ケア部会を年4回開催で、最終は2月27日の予定です。運営事務局会議は毎月開催しています。緩和ケア研修は資料の一覧で確認ください。緩和ケア研修会指導者の会は、研修企画責任者が課題を共有し合う会で、2月9日に開催しました。緩和ケアフォローアップ研修会は、神戸市立医療センター中央市民病院に担当頂き、Webで開催しましたので、詳細は報告書を参照してください。緩和ケアチーム研修会は、加古川中央市民病院の担当で2月9日にWeb開催した。緩和ケアチームピアレビューは、10月13日、神戸市立西神戸医療センター、12月4日、県立はりま姫路総合医療センターの2施設で実施した。報告書を添付しているので確認ください。症状緩和のための専門的治療体制に関する実態調査は、毎年アンケート調査を実施している。主に神経ブロック、緩和的放射線治療、緩和IVRに関して兵庫県がん診療連携協議会のホームページで公開している。都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会の緩和ケア部会は、12月6日に参加した。
令和7年度の活動計画は、前年度を踏襲した形で活動するが、働き方改革もあるので、会議は極力減らす方向で予定している。緩和ケア部会は年4回から3回に減らす。運営事務局会議も毎月開催から偶数月の隔月開催に減らすことを検討している。小集団活動の運営は継続予定だが、各研修会やピアレビューは基本的には定日の時間内での開催を検討している。土曜日の開催が増えているので、代休などで普段の通常業務を圧迫することがあるので、極力、省略できるところは省略して必要最小限のものにしていきたいので、部会で検討している。
なお、緩和ケア部会の各研修会の案内、連絡事項等が、各施設内で周知されていない医療機関があるので、必ず周知をお願いしたい。
⑥「地域連携」部会関連
令和6年度の活動報告は、毎年年度末にお願いするアンケートで、がんの地域連携パスについては登録件数が年1,485件、令和6年度までの累計で14,339件とビックデータになっている。内訳は乳がん6,657件、以下資料のとおりで、5大がんの中では肝臓がんが少なく、後発である前立腺がんのがんパスがすごく利用されている。がんパスの見直しが必要なものは、各ワーキンググループで検討いただき、修正を進めている。がん地域連携についてのアンケートではWebによる退院前カンファレンスを49施設中、21施設で行われていて、コロナ下で始まった遠隔診療は、令和5年度で167件と多くはない。この診療のノウハウを均てん化していく必要があるかなと思う。がんゲノム医療は、実施できている施設とできていない施設あると思うが、49施設中20施設が実施し、治療につながったのは一般的には10%程度と言われているが、16%であった。兵庫県はがんパネル遺伝子に関わっている医療者或いは患者・家族の方の意識が高く、このように治療につながることを均てん化できる仕組みがいると思っている。
令和7年度もがんパスの使用状況の確認、課題や修正を行い、がん地域連携に関する課題に関して、もう少し詳しく調べたい。
〇胃がんESDと肺がん地域連携パスの改訂について
胃がんESDパスについては、1年目、2年目は半年毎の検査になっているが、何回もの検査は難しいと思うし、再発が少ないなどの理由で、検査件数を減らしてかかりつけ医の先生にある程度担っていただくように、「必須」を「できれば」に改訂した。それから連携計画と自己チェックシートを充実させて分かりやすくした。胃がんの原因であるヘリコバスターピロリ菌の現感染、未感染、既感染あるいは除菌の有無に関して記載できるようにした。以上、検査を間引いて、より使いやすいようにした。
肺がんパスについては、肺がんグループで検討いただき、現行パスの病期の取扱い規約が2025年に新たな版が出たのでそれに合わせて変更いただいた。
〇肝がん地域連携パスの改訂について
肝がんは特殊性があって連携パスがほとんど進んでいない。WGの中でアンケートを取ってコメント頂いた。パス使用の施設は5施設あったが、今年度は対象の患者がいない。その原因は、専門病院の受診が原則3か月ごとであること。3か月毎のエコーと6~12か月毎のCT/MRIが必要なため連携する余地が少ない。連携協力施設が他の癌に比べ非常に少ない。肝機能のフォローのハードルが非常に高い。背景の肝障害の病態が様々である。代償期の肝硬変、投薬など必要のない患者さんはかかりつけ医に通院する必要がない。非代償期でも軽度の場合は、3か月前に画像診断や血液検査を行うことも多いので、3か月の投薬を希望して、かかりつけ医に行く人がいない。それから非代償期の中等症以上、いわゆる肝硬変で腹水とか食道静脈瘤の可能性がある状態になると、かかりつけ医では対応困難で専門医療機関での管理が必要になる。そのような状況での肝機能のフォローアップが厳しい。
また、最近は薬物療法が増えてきて、免疫チェックポイント阻害剤とか分子標的薬の組み合わせのようなことで肝臓がんとなると、多肢にわたるプロトコールで患者管理が難しいといった理由で、連携パスが進まない。
現実、どのような状況ならパスの対象となるかは、他疾患、おそらく糖尿病、高血圧といった合併症の人で、1~2か月に1回程度かかりつけ医に通院している患者さんで、肝臓がんの人。代償期で肝機能の変化が急激に起こりにくい患者さん(肝硬変で腹水、食道静脈瘤の可能性がない)なら可能かもしれない。ほかには遠方で通院頻度を減らすことを希望する患者さん、承認される可能性は少ないかもしれないが薬物療法で副作用チェックが必要な患者さんであれば、対象となり得るかもしれない。当院医師がフォローしている肝臓癌のパスの導入例は、腹腔鏡下肝部分切除した離島に住む漁師さんが姫路のクリニックに糖尿病で通院し、がんセンターに肝がんで通院しているケースで、うまくパスが回っているということだった。
また、肝がんパスも規約のこともあり、背景に以前のB型、C型肝炎から今は主に脂肪肝が多くなっていることで、まだ案ですが、文言に修正(資料赤字)を考えている。治療が以前と変わって薬物療法が増えてきたということもあって、手術のところに「開腹」「腹腔鏡」「ロボット」という文字、全身化学療法。これに分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬の内服/静注という項目を入れたが、ワーキンググループで少し検討したい。
によっては腹水、食道静脈瘤もフォローの先にあるということで、かかりつけ医では煩雑で手に負えないことがある。肝がんの診断は画像診断が全てで、確定診断がつくものもあれば、境界病変で疑わしいとか可能性を否定できないみたいな境界病変が多いとなると、基本的には3か月毎のCT/MRIが必要になる。そうすると治療する病院に通院してフォローすることになるので、かかりつけ医等に行く機会がなくなる。また、最近の化学療法は、化学療法の組み合わせによる副作用は診てもらえる病院も少ないようなことで、今後は無理なく連携できる病院とか専門医療機関があればお願いする程度で進んでいくしかないと考えます。今後、このような問題をもう少し詳細に詰めたい。
〇胃がんESDと肺がんパスの改訂案の承認について
改訂案に対する異論はなく、承認された。
(4)がん生殖医療について(資料4/PDF: 187KB)
兵庫県がん・生殖医療ネットワークの運用状況は、2024年1月から12月までに女性は44名、男性は38名にカウンセリングを行い、原疾患の内訳は女性の乳がん25名で最多、男性では白血病が最多、平均年齢も28.5歳前後という状況です。登録施設は英ウィメンズクリニック、兵庫医大、徐レディースクリニックが参加している。それぞれ特徴があって、英ウィメンズクリニックは卵子凍結、精子凍結が多い。兵庫医大は卵巣凍結が多いとなっている。兵庫県全体では、卵子凍結22名、精子凍結36名になる。女性における妊孕性温存については、2016年からネットワークが開始され、2021年からは研究促進事業として助成金が得られるシステムが開始、2024年には実施数は41名行われた。男性については2020年10月から対象とし、データは2021年からですが、精子凍結、精巣凍結が行われた。来年はネットワーク開始10年になるので、妊娠率や利用率を算出したい。
(5)がん患者医科歯科連携事業について(資料5/PDF: 146KB)
令和6年度は例年通りの事業内容を行った。研修会はハンズオンセミナーを1回行い、講演会は、東京歯科大学の柴原先生に口腔がんの粘膜の見方について説明いただいた。
令和7年度については、口腔がんの講演会として、タレントの堀ちえみさんと先ほどの柴原先生との講演会を考えている。この二人は何回か全国で講演されている。
(6)小児がんの進捗状況について(資料6/PDF: 3.5MB)
小児がんの第4期がん対策推進基本計画の位置づけは、小児がん拠点病院事業の第3期の2年目です。2023年の情報公開によると、正確な数字ではありませんが、約3,000名位の小児がんの症例が100余りの施設で診療を受けている。基本計画でもまず、集約化と均てん化という一つのキーワードで展開することになっている。全国に現在15の小児がん拠点病院が配置されている。集約化に関しては、この10年の間に相当に集約化が進み、兵庫県では県立尼崎総合医療センターと神戸大学の3施設でほぼ100%の小児がんを診ている現状にある。県内では集約化が進んでおり、全国でも比較的診断実績を多く積み上げている地域になる。それを支える小児血液がんの専門医6名、日本血液がん学会の専門医10名、造血細胞移植学会の認定医8名といったような人員で診療にあたってる。
この事業は、拠点病院と連携病院1Aで日本全体の7割の患者さんを均質な治療でカバーするコンセプトで計画は作られ、実際は7割を超えて8割に迫る勢いで集約化が進んでいる。兵庫県内では、10施設でそれぞれ役割を分担しながら小児がんの診療を展開し、県立こども病院、県立尼崎総合医療センター、神戸大学医学部附属病院の小児科の先生と定期的にWeb会議で連携し、支え合って診療を展開している。一方県外では、小児がんの患者さんは少子化もあって、その数が減っており、需要を満たす意味もあって県外からの受入れも始めている。資料の地図には新規小児がん患者が極めて少ない地域が色分けされ、中四国、四国3県、参院、山口県など非常に症例数が少ない地域があるので、この地域と連携を深めている。
人材育成の点では、香川大学と教育研修施設群を形成して連携している。一般的な臨床については、ドクターヘリやドクタージェットも活用しながら救急集中治療を含むあらゆる小児がんに対応する体制を組んでおり、そうした形で患者さんを集めて診療している。
2020年12月から始めた遺伝子改変T細胞療法は、この2年間で症例と経験を積み上げ、今5例目を準備して6例目も間もなく紹介され、免疫細胞療法に関しては力を入れているが、残念ながら細胞数が十分足らない。規格外品の扱いについては治験を用いながら何とか希望される患者さんに免疫細胞療法を提供できるようにしている。少子化では、ドナー不足で移植も少しずつ減っているので、GBTの管理を充実させるためにECPを導入することを始めている。小児がんの領域で難治の神経腫といった固形腫瘍は、当院で患者さんがクラウドファンディングを展開して海外への渡航費用が確保され、こうした患者さんの希望に対応しながら、イタリアの事務局と当院チームのドクターが日夜連絡を取りながら準備を行っている。
当施設は神戸陽子線センターと隣接しているので、全国から陽子線治療の患者さんを受入ており、特に中四国から多くの患者さんが来られて多くの県外患者さんを扱っている。
ゲノム医療については、Foundation One Liquid、Guardant360、Gen Mine Topといったゲノムプロファイリング検査が、小児でも次々に保険適用となっており、昨年9月にヘムサイトが承認されたが保健適用の疾患・病期は未確定で整理が必要である。ドラッグラグ解消と検査ラグ解消を並行して実施し、併せて治験をしっかり進めている。
治験については、それを担う人材がいないため、国立がん研究センターと全国の小児がん拠点病院が人材育成で連携することになった。再発LCH、移植のCMY難治感染症、再発AML、中間リスクALLなど、医師主導の治験を展開している。該当患者さんがあれば相談ください。
医療上の必要性が高い未承認薬や適用外薬は国主導で開発申請したり、研究班が立ち上がったりしているが、医薬新薬について昨年10月23日に通知が出て、医薬品の条件付き承認という新しい制度がスタートすると聞いている。欧米における条件付承認の制度に準じた制度で、海外で承認を受けているが日本では承認がない新薬を、国内治験をスキップして条件付承認を行っている。これを小児がんのドラッグラグの解消の切り札的な役割ができないかという提案があった。
移行期医療については、3万人の小児がん経験者がどのような晩期障害に苦しんでいるかという疫学調査を行い、約6割の患者さんに晩期障害が認められ、複数の晩期障害を持つ人は25%だった。神戸大学附属病院に兵庫県移行期医療支援センターが設置され、お世話にいなりながらきめ細かなフォローアップができるように協力している。
環境整備については、高等教育に関して厚労・文部省からの通知により、高校生患者の教育保障、教育支援で単位認定が取りやすくなり、県教育委員会の協力を得ながら支援を行っているので、該当する方がおられたらお役に立てるので声をかけて頂きたい。
緩和ケアの医療については、2013年に緩和ケアチームが発足して10年位と歴史が浅いが、緩和ケア「ニコニコサポートチーム」も県立がんセンター、県立はりま姫路総合医療センターの協力を得ながら体制が整い、今年度の小児緩和ケアの指導加算が新設されて追い風となっている。
(7)その他(資料7-1/PDF: 18.6MB・資料7-2/PDF: 2.2MB)
① 心血管フォローアップ手帳について
前回の幹事会で検討いただいたサバイバー手帳は、皆様からご意見を集約して、一冊の手帳に仕上がった。がん治療の中でも一部に心血管毒性がある抗がん剤、放射線治療などがある。がん治療終了時に主治医はその晩期合併症についての説明をしているが、がん治療が終わるとサバイバーの方は説明されたことを忘れ、晩期障害による自覚症状があって初めて医療機関を受診されることが多い。目次にはさまざまな項目を記載しているが、まずは、第1版としてのフォローアップ手帳の目的は心血管合併症を早期に発見することであり、そのことを医療者側およびサバイバー患者さん双方に意識してもらうためにこのフォローアップ手帳の作成に至った。
この手帳は、医療者側が記入するだけでなく、患者さんにも協力いただき、共同で作成していく手帳であるという位置付けをしている。青く色付けしているところは医療者側が記入する部分で、ピンク色は患者さんが記入される部分になります。
当初は、がんサバイバー患者さん全体に応用できる医療情報を収載した手帳はどうかとも考えた。たとえばかかりつけ医やアレルギー記録、がん治療だけではなく、社会面や経済面の相談部署の紹介や調整など項目が多肢にわたるサバイバー手帳にしようかとも考えたが、そのスタイルでは各部署との連携調整なども必要であり腫瘍循環器科だけでは対応が困難と思われたため、今回は“心血管フォローアップ”のための手帳ということにしてがん治療による心血管合併症のリスクについての記載欄を主体とした。アントラサイクリン系薬剤の累積投与量と最終投与日を記載する。殺細胞性の抗がん剤だけでなく、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤なども心血管毒性があり、その欄を設けた。その下に記載欄のある放射線治療のところはもう少し広くスペースを取ればよかったかと思う。照射の部位、治療期間、照射量を記載する。定期的な心エコー検査や採血(BNPやトロポニンI、Tなど)フォローしていくにあたり、治療前、治療中、治療終了時の心エコー所見や再検査の推奨時期も記載する。これを記入した時点で、何年ごとに心エコーが推奨されるか、BNPが上昇した時、症状が出た時などの受診で良いかなどを患者さんに書いて渡せるので、患者さんもフォローの必要性について認識していただきやすくなると考えている。
また、がん治療と直接は関連しない記載事項ではあるが、体内金属がある場合にMRI検査の都度それはMRI検査可能な金属であるかなど確認する必要があり、非効率的であったため、手帳の中に体内医療機器の欄を設けた。
がんにはその血栓症がよく合併することがあるので、抗血小板剤・抗凝固剤の内服の有無、深部静脈血栓の既往についての記載、また、がん以外の病気の既往歴も書いてもらい、がん以外の手術に関しても大まかに記載する、という内容の手帳になっている。
実際、年明けから数名に使ってみたが、腫瘍循環器科としては心エコー所見を書く欄をもう少し広く取ればよかったが、箇条書きにすると経過がわかりやすいことに気づいた。いずれ他の病院でも使って頂いて、ご意見をいただけたらと思います。
この手帳をどのように活用していくかをこの場で検討して頂きたい。例えば協議会のホームページに掲載いただくとかはいかがですか。
⇒ 昨年度から案ということで出来上がった。色々ご意見があるかもしれません。細かすぎるとか足らないとか。とりあえず叩き台を作成して冊子にもしておりますので、ご利用いただいてご意見を頂けたらと思います。ダウンロードできるようにしておけばよろしいでしょうか。(幹事長)
⇒ がんパスと同じように、また協議会のメンバーが使いやすいように、とりあえずホームページにアップして、ダウンロードできるようにした方が良いのかなと思います。がんパスと同じように不都合なところがあれば改訂したらいいのでは。(県立丹波医療センター)
⇒ 多くの病院で使っていただけることを目指しているので、そのようにさせていただきます。(幹事長)
⇒ 県立がんセンターのホームページにも掲載可能でしょうか。(県立がんセンター腫瘍循環器科)
⇒ 可能です。こども病院でもAYA世代から繋がっていくことも多いかと思いますし、おそらく同じようなことをされていると思いますが。(幹事長)
⇒ こども病院で活用しているこのようなフォローアップ手帳には、乳がん患者さんがそのような分子標的治療薬とか対応できてないところがあるので、是非協議会のホームページに載せて頂いて活用できるようにして頂ければ大変助かります。(県立こども病院)
⇒ 改訂が必要な点があるかもしれないが、また今後マイナンバーカードがどう動くかわからないが、当面、これで承認いただけますか。(幹事長)
⇒ 承認いただいたということで、ホームページに掲載します。(幹事長)
② 希少がん対策について
兵庫県の希少がん対策として、今後の「希少がんネットワークの構築」を提案する。
希少がんの年間発生率は10万人あたり6例未満と少なく、診療上の課題が他のがん腫に比べて多いとされる。個々の希少がんの症例数は少ないが、種類は190に及び、全がんの15~20%を占めるため、決して無視できない腫瘍群である。希少がん対策の課題として、適正な診断・治療へのアクセス不足、病理診断の不精確さ、診療・治療開発の遅れ、医療関係者と患者双方の情報不足が挙げられる。
国の「第4期がん対策推進基本計画」では、希少がん・難治性がん対策として、希少がん中央機関を設置し、診断支援や専門施設の整備を進めている。今後の施策として、高度かつ専門的な医療へのアクセス向上のため、診療拠点病院の役割分担と連携体制の整備が求められている。
兵庫県の「がん対策推進計画」においても、質の高いがん医療の提供体制構築に加え、がんゲノム医療や希少がん・難治性がんの専門医療へのアクセシビリティ確保が掲げられている。
希少がんセンター事業としては、2014年に国立がん研究センターに希少がんセンターが開設され、情報提供、講演会、希少がんホットラインでの相談支援、診療研究などが行われている。希少がんネットワークの構築については、全国どこでも適切な診断を可能にする、新たな治療の迅速な提供、患者に寄り添った相談・情報提供を充実を目的に、国立がん研究センターを中央機関とし、各地域に中核拠点が整備されている。
現在、全国6施設に中核拠点(希少がんセンター)が設置されており、近畿地方では大阪国際がんセンターが中核拠点に指定されている。大阪国際がんセンターが中心になって「近畿地方の希少がんネットワーク」が設置され、2024年8月に第1回オンライン会議開催された。近畿の6府県から都道府県がん診療連携拠点病院が参加して、兵庫県からは県立がんセンター院長と藤田が参加した。
兵庫県における希少がん対策として、「希少がん患者が必要な情報にアクセスでき、速やかに適切な医療につながることを目指す」を目標とした。そのための取組みとして、拠点病院等の役割分担を整理し、施設間の連携を促進するとともに、情報の発信および相談の支援体制の確立を進めたい。
今後の協議事項として
(ア)県内の希少がん診療情報を共有と、施設間連携の促進
- 国指定の拠点病院で連携して希少がん診療の情報を共有する。
- 共有する部署は、がん相談支援センターが中心になって行う。
- 共有する情報は治療が可能な施設と治療実績等
(イ)希少がんに関する情報発信と相談支援体制の確立
- がん相談支援センターが医療者だけでなく、患者・家族にも情報を提供する
- 提供する情報は、診療可能な施設、疾患情報、希少がん相談窓口等
今回の提案内容は、これらの目標と取組事項を実行するための希少がん対策を協議する場を設置し、希少がん患者のサポート体制の構築である。国指定のがん診療(拠点)病院と小児がん拠点病院において、希少がん担当者(マネージメントできる医師)を選定いただいて、今後協議を行いたい。
⇒ 希少がん対策を協議する場としてワーキングないしは部会の設置を承認いただきたい。(幹事長)
⇒ 国は希少がん対策に力を入れている。中央機関と中核拠点病院を6つ指定し、全国ネットワークを作った。近畿では大阪国際がんセンターが中核拠点病院になることで、6府県で近畿の希少がんネットワークを作ることになった。兵庫県は、国指定のがん拠点病院等が中心になって、まずはネットワークのあり方について相談したいので、当院の希少がんセンター長から改めて国指定病院へ希少がんのワーキンググループの代表者1名を選出してほしい旨のメールを配信するので、対応をお願いしたい。(議長)
⇒ 丹波医療センターは、国指定のがん診療拠点病院であったが、指定要件が厳しくなって現時点では外れているが体制は維持している。県域では赤穂市民病院と当院が、国指定のがん診療病院になっているが、提案のあった希少がんの患者さんを取残さないという立場から参画させてもらえればありがたい。がん診療拠点病院の指定要件である放射線専門医の確保に目処が付いてきたので、ご理解をいただければ助かる。(県立丹波医療センター)
以上に基づき、希少がん対策のワーキングないしは部会の設置、及び国指定のがん診療連携拠点病院、がん診療病院、小児がん拠点病院の参加が承認された。
〇意見(提案)
・兵庫県のがん検診率について(ひょうごがん患者連絡会)
兵庫県のがん死亡率が全国でも20位前後と良くなっている。一方の検診率はどの部位をとっても大体40位前後である。この検診率が良くなればさらに死亡率を減らせる。検診率について県から会議などで発表していただいて検診率を上げてほしい。がんは医療体制だけでなく、がん予防・早期発見が、がん教育につながっていく。肝がんの患者会を40年やっているが、やはり医療体制と検診率の2つを上げたいとやってきた。がん治療は早期発見が大事だから、「検診」という言葉をあらゆる会議の中で使われることを提案する。(ひょうごがん患者連絡会)
⇒ 健康づくり審査会対がん戦略部会でも検診率の話はいつも話題になる。兵庫県は検診率が低いという話で、検診率を上げる対策として無料券を発行したりしているところもあるが、なかなか上がってこない。国で何か実施する案など、情報はありますか。(議長)
⇒ ご指摘のとおり、兵庫県のがん検診率は全国の平均に比べて大体4~5ポイント低い。全国的にみても40位ということで、いろいろ指摘をいただいたり、先般の県議会においても、がん検診率の向上を指摘いただいている。市町のがん検診取組アップの働きかけとか、職域に対する働きかけとか言っているところですが、効果が出ていない。長期的に見れば検診率は上がっているが、全国的な平均値には追いついていないのが実情である。基本計画の改訂に合わせて、国から新しい事業を実施することを期待していたが、特に出てきていない。残念ながらこれまでの取り組みを地道に進めていく必要があると考えている。良い提案があれば事業化を検討したい。がん検診状況については、こういった幹事会の場を活用しながら報告させていただき、皆様の意見をいただきたいと思っている。(県疾病対策課)
⇒ 個別な案件になるので、何か特殊な状況があると思いますが、一般論では他病院でも相談は受けられます。その病院にはがん相談支援センターがない病院だと思われる。自分の病院で相談しにくいから他病院へ相談した場合は、病状から一般的な相談になる。できればご自身の病院のがん相談支援センターで相談された方が良いのではという答えは十分想定できる。(情報・連携部会長)
⇒ 肝炎の検診率は全国で7~8番目である。がんの死亡率がこの20年位で良くなっていると思う。やはり検診率を上げることが、その医療体制と両輪でいかないと良くならないと思うので、検討してください。(ひょうごがん患者連絡会)
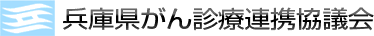
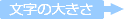




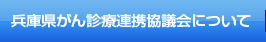
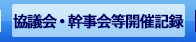


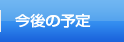
 令和6年度 第2回 兵庫県がん診療連携協議会幹事会 議事録
令和6年度 第2回 兵庫県がん診療連携協議会幹事会 議事録